
みなさんこんにちは!埼玉県にある「ミニバン専門店ラインアップ」代表の菊池です。
交通事故に巻き込まれた場合、保険に加入していると各種補償を受けられるため積極的に加入したいものです。
しかし、相手が保険に加入していないと思うような補償を得られない可能性があるのです。
では、無保険車との間で衝突事故が発生する場合、どのようなリスクがあるのでしょうか?
本記事では、無保険車と衝突するリスクを紹介するとともに、事故後に払わせるためのテクニックや加入を検討すべき保険プランを紹介します。
無保険車と衝突する3つのリスク


無保険車との間で事故が発生した場合、主に以下3つのリスクがあります。
各リスクについて、詳しく解説します。
賠償資力ゼロで補償不足
自動車の場合、自賠責と呼ばれる必ず加入しなければならない保険と、任意保険と呼ばれる加入するかどうかは自分で判断する保険があります。
自賠責の場合、必要最小限の補償しか得られないため、基本的には任意保険にも加入するのが一般的です。
具体的には、自賠責の限度額は傷害120万円、後遺障害75万円から4,000万円、死亡3,000万円となります。
例えば、寝たきりなど重度後遺障害となった場合の実損は、1億円を超えるのが普通となり差額は回収不能になりがちです。
また、加害者の財産を調べると無職・車両ローン滞納中というケースが多いです。
以上のように、もし事故に巻き込まれて大きな賠償を請求したくても、泣き寝入りのようになってしまう可能性があります。
物損は自己負担になる恐れ
自賠責保険の場合、人身事故に対する補償のみとなり物損事故には適用されません。
よって、自動車同士の衝突による破損であったり、ガードレールなどの建造物の損害であったりする場合、自賠責保険では補償されないのです。
自動車の修理代金や、修理が完了するまでにかかる代車の費用は、後述するような方法が適用できない場合、相手から負担してもらえなければ自己負担しなければなりません。
車両だけでなく、荷物(楽器・ノート PC 等)やガードレール破損についても同様であり、自分で負担を強いられる場合があります。
示談交渉が当事者どうしで難航
無保険車との間で事故が発生した場合、示談交渉が難航しがちです。
なぜ難航するかと言えば、相手が任意保険に加入していないことイコール保険会社による示談交渉のサポートを受けられないためです。
これにより、被害者自身が加害者と直接交渉しなければならなくなります。
この時、加害者の誠実な対応や支払い能力の有無が不確定であるため、交渉が長期化したり、十分な賠償金を受け取れなかったりする可能性があるのです。
具体的には、連絡が途絶えることが多く、対面しても逆ギレされたり脅迫されたりするケースがあります。
また、分割で月5千円を支払うなどの提示は示談交渉時の典型的なパターンです。
交渉の“心理戦”は避けることができず、精神的な二次被害を招く可能性があります。
事故後に「払わせる」ための3ステップ


無保険車との間で事故が発生した場合、任意保険に加入していないからと言って泣き寝入りすることは絶対に避けたいものです。
そこで、相手に補償させるためには以下のステップでアクションを起こすことをおすすめします。
各ステップの詳細は、以下の通りです。
証拠を固めたうえで自賠責へ被害者請求
自賠責の範囲で補償してもらうためには、証拠固めが重要な作業となります。
まずは、どのような被害が発生したかについて以下の必要書類を準備してください。
- 交通事故証明書
- 診断書
- 診療報酬明細
- 修理見積
- 休業損害証明
以上のように、車両や人体への被害以外にも、休業を強いられた場合の補償を含めた証拠を集めることが重要です。
書類が揃えば、相手が応じなくても請求することは可能となります。
補償額は、振込まで平均1ヶ月から2カ月程度かかるのが一般的です。
自賠責不足分は政府保障事業で請求
自賠責の場合、必要最小限の補償しか受けられないため、金額的に不十分な場合が多いです。
そこで、自賠責不足分は政府保障事業に請求しましょう。
政府保障事業とは、自動車損害賠償保障法に基づいて自動車事故の被害者を救済するための制度となります。
自賠責や共済に加入していない自動車による事故やひき逃げ事故といった、加害者から十分な賠償が受けられないケースで、国が被害者の損害を補償します。
補償内容は自賠責保険と同程度の範囲と限度額となり、以下の補償が含まれます。
- 治療費
- 休業損害
- 慰謝料
- 後遺障害による逸失利益や慰謝料
- 死亡した場合の葬儀費
- 逸失利益
- 遺族の慰謝料
なお、健康保険と労災給付分は差し引かれ、物損は対象外となります。
政府保障事業は、事故翌日から3年以内、死亡事故の場合死亡日翌日から3年以内に申請しなければなりません。
請求キットは損保窓口かポータルサイトでダウンロードでき、領収書や戸籍謄本など添付して提出します。
弁護士特約 → 訴訟 → 差押えで回収を図る
自分が加入している任意保険で、弁護士特約が付いている場合は弁護士に依頼する方法も有効です。
弁護士特約とは、交通事故や日常生活におけるトラブルで弁護士に相談したり依頼したりする際にかかる費用を補償する、自動車保険の特約です。
特約が付いている場合、着手金や報酬を最大300万円まで保険会社が負担してくれます。
これにより、相手に対して裁判を起こしやすくなるのです。
裁判の流れとしては、内容証明を送付して訴訟を起こします。
この際、少額訴訟も検討すると良いでしょう。
そして、裁判の結果勝訴が確定すれば、口座や給与を差押えることで賠償を受けられます。
差押え前に預貯金を逃がされないように、仮差押え申立てするのが有効です。
今すぐ加入を検討すべき保険プラン


無保険車との間で、いつどこで事故が発生するかを予測することは不可能です。
よって、いざという時のことを考えて現在加入している保険の内容を見直すことも検討したいものです。
今すぐ加入を検討すべき保険プランをまとめると、以下のようになります。
| 補償 | 推奨水準 | なぜ必要か | 保険料の目安* |
|---|---|---|---|
| 人身傷害補償 | 無制限 | 過失割合0でも実損満額カバー。歩行中・自転車にも◎ | 年間+4,000円〜6,000円 |
| 無保険車傷害特約 | 2億円〜無制限 | 死亡・後遺障害時に自賠責超過分を給付 | 年間+300円〜600円 |
| 車両保険 | エコノミー型以上 | あて逃げ・相手不明の修理費を補償 | (車格次第)+1.5万円〜3万円 |
| 弁護士費用特約 | 上限300万円 | 交渉・訴訟を丸投げ、費用倒れリスクゼロ | 年間+1,000円〜2,000円 |
*通販型保険の普通車・20等級を想定
車両保険は「車対車+限定A」でも無保険車やあて逃げをカバーする会社が増加しています。
しかし、年間の負担額が最大3万円程度増加する場合もあるため費用対効果を考えて追加すべきかどうかを判断する必要があります。
1世帯1契約あれば、家族全員が他人名義の車で被害に遭っても特約が使えるという点を含めて、上記の特約の加入を検討しましょう。
まとめ:泣き寝入りしないための鉄則
無保険車との間で事故が発生した場合、泣き寝入りしないようにするためには、まずはリスク把握をしっかり行うことが重要です。
具体的には、自賠責の限度と物損の穴を理解しておく必要があります。
次に、証拠確保として証明書・診断書・修理見積を事故直後より入手する行動を取りましょう。
そして、被害者請求から始めて、応じない場合は政府保障を活用しつつ訴訟・差押えまで進めましょう。
しかし、莫大な時間と労力がかかることを考えると、人身傷害+無保険車傷害+弁護士特約は“鉄板3点セット”として加入しておきたいものです。
最低限この4ステップを踏めば、無保険車事故でも経済的ダメージは最小限に抑えられます。
これからお車を購入される方はもちろん、現在すでに任意保険にご加入中の方も、この機会にご自身のプランを見直してみてはいかがでしょうか?
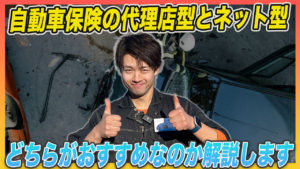
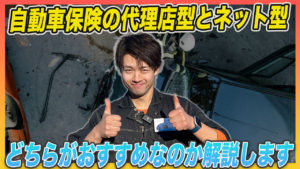




コメント